【総】より一部紹介 小見出し等も紹介します
弁財天(弁才天)とは
弁財天(弁才天)といえば、七福神の紅一点で、琵琶を抱えた美しい女神の姿を思い浮かべる人が多いと思われる。またそのご利益も、財福や音楽、芸能を中心として、さまざまなものがあるイメージが強いであろう。しかし元から今のような姿やご利益を持ち合わせていたわけではなく、時代の要請などに合わせ、ご利益を変化させたり増やしながら現在に至ったようである。また弁財天という呼称も、七福神として定着した頃からの呼び名と考えられ、古くは弁才天の呼称が一般的であった。以下その源であるインドから、順に見ていくこととする。
インドでの弁才天
弁才天の元の名とされる「Sarasvati(サラスヴァティー)」という語は、「Saras(サラス:湖、池、貯水池などの意)」と「Vat(ヴァト:有するという意)」を合成した、「湖(水)を有する」という語の女性形であるという。サラスヴァティーはインドに流れる河の名前とされ、アフガニスタン南東部の現ザーブル州、カンダハール州などを流れるアルガンダブ河とする説や、インド北西部の現ラジヤスタン州に流れる河を指すとする説などがある。
このサラスヴァティー河は、バラモン教の聖典のうち最も成立が古いとされる「Rgveda (リグ・ヴェーダ)」において、河辺の人々に富と食と勇気と子孫とを与えるものとして賛美されているという。それ故に河そのものが神格化され、女神の名となったと考えられているが、先に見たようにサラスヴァティーという語そのものには、「弁才」という意味がみられない。またそのご利益も、リグ・ ヴェーダの記述に見られるように、豊穣などの恵みをもたらすとは考えられていたようだが、現在我々の知るところである弁才天のご利益は、もとから全てが備わっていたわけではなかったようである。
インドにおいて、言語・談話・弁舌・音楽などを司る神としては、 弁舌の女神「Vac(ヴァーチ)」が古くから崇拝されていた。サラスヴァティー河が神格化され、その地位が向上して行くにつれてこのヴァーチと同一化し、現在我々が知るような弁舌・学問・知識・ 音楽などのご利益を備えたという。そしてついには梵語や梵字の創作者ともされ、梵天(ブラフマー)の妃とされるにいたり、さらに多様な性格やご利益を付与されていったようである。
その造形に目を転じると、古くは単独で造られることはほとんど無く、経典上も関連の深い吉祥天と対にして造られることが多かったようである。現存最古の作例でもある東大寺三月堂の塑像や、鎌倉時代の初めに造られた京都の浄瑠璃寺旧蔵(現東京芸術大学所蔵) の吉祥天厨子絵などが、その好例であるといえる。また鎌倉時代以前の実作例となると、別尊雑記(図版二六)や諸尊図像集(図版二)といった図像類には見られるものの、その数は決して多くはない。
一方、「大日経」は密教経典の代表的なもので、両界曼荼羅のうち胎蔵界曼荼羅の拠り所となっている経典である。この「大日経」 を拠り所とする弁才天は、妙音天とも呼ばれ、胎蔵界曼荼羅の外金剛部にその姿が見え、菩薩などと同様に上半身裸で、二間(二本の腕)で琵琶を弾く姿で描かれている。こちらは「妙音」と呼ばれることや、琵琶を持つことからも想像がつくように、音楽神としてのイメージが強調されている。
実作例に目を移すと、空海在世中に描かれた京都・神護寺の高雄曼荼羅をはじめ、数多く存在する両界曼荼羅には、その数だけ姿を認めることができる。しかし単独像となると、京都・白雲神社に伝わる妙音天像や、鎌倉・鶴岡八幡宮の弁才天像 (図版三)などが有名ではあるが、やはり数が限られたものとなる。 鶴岡八幡宮白雲神社の像の前では、琵琶の秘曲の伝授が行われていたといい、鶴岡八幡宮の像も、銘文から中原光氏という八幡宮楽所の一流の楽師によって、舞楽院に奉納されたことが判る。これらは音楽神として崇められ、ご利益が期待されたことがうかがえる。
なお、その後、琵琶を持った姿は中国風の女神の服装へと変化し、七福神の弁財天の原型となっていくことになるようである。
姿とご利益の変化
八臂の弁才天像の頭上に、老人の頭をした白い蛇が載っていることがある。これは宇賀神という神で、古代の穀物神である宇迦之御魂とも、如意宝珠が姿を変えた、無限の福徳をもたらす神ともいわれる。この宇賀神の載った弁才天を説くものには、「弁天五部経」 と呼び習わされる五部の経典が知られているが、これらは全て日本で撰述された偽経とされている。
はっきりした成立年代は判らないが、横浜市金沢区の称名寺に、 弘長元年(一二六一)に伊豆山で書写された『仏説宇加神将十五章子獲得如意宝珠経』(図版三三) が伝わっていることや、延暦寺僧である光宗の作で鎌倉時代末期に成立したとされる「渓嵐拾葉集」 に、類似する経典の名が見られることから、鎌倉時代後期までには成立したと考えられている。ここに見える弁才天の姿は、八ぴで剣や弓を持つ点では、「金光明最勝王経』に拠る弁才天と変わらないが、 宇賀神を頭上に蔵くことのほか、如意宝珠と鑰(鍵)を持つ点が異なっている。
この後、弁才天の頭上に載る宇賀神は大黒天であるという解釈が生まれたり、弁才天は三宝荒神という荒ぶる強力な神を押さえ、その力を福徳に変換する存在であるなどという、まるで観音菩薩と飲喜天との関係のような解釈も生まれてくる。ご利益も福徳神としての性格が強調されるに留まらず、さまざまなものを取り込んで、次第に全能に近い存在にまでなっていったようである。それはブラフマーの妃とされてからのサラスヴァティーが、多様な性格やご利益を付与されていった様子に近いといえるのかも知れない。
そのご利益の幅が広いこともあってか、現在われわれが目にする八臂の弁才天は…(以下略)
【解説】より一部紹介
金光明最勝王経 一〇站 江戸時代 個人蔵
紙本木版刷 折木各縦三〇・〇×横一二八 「金光明最勝王経」は、「法華経」、「仁王経」と並び、わが国で護国三部経典と称され尊ばれた経典である。全一〇巻のうち、巻七の「大弁才天女品」に八臂(八本の腕)の弁才天が説かれており、弁才天の根本経典の一つとなっている。 本品は正徳三年(一七一三) 一月一一日に摺られ、直治寂紫子という人物が願
主であったことが刊記からうかがえる。また箱書によれば義栄という僧侶によって、江ノ島に文久四年(一八六四)に奉納されたことが判る。 なお、表紙に十六弁菊花紋が見られるのは、岩本院が仁和寺末であったことを示すものと思われる。
重要文化財 諸尊図像集のうち天部等 一巻 鎌倉時代
紙本墨書 縦三〇・六×横一四一六・八
顔料を用いて濃厚な彩色の施された図像集。本書は、称名寺第二代長老の銀何周辺で収集されたと考えられ、観音部、天部等の二巻が現存している。本書に収録された図像のうちには、東寺観智院旧蔵本(現MOA美術館所蔵)に類似する図像があるとされているが、完全に一致する図像は今のところ知られていない。
弁才天は天部等の巻に含まれ、二間(二本の腕)で琵琶を奏でる座った姿のもの、八間で武器を持つ立った姿のもの、大振りの冠を被った箜篌(竪琴のような楽器)を弾く座った姿のものが描かれている。
重要文化財 弁才天坐像 一 文永三年(一二六六)
鶴岡八幡宮 所蔵 木造彩色 像高九五・七
横座りの姿勢で、琵琶を奏でる姿に表された二階の弁才天像。上半身は裸形で、 下半身は下衣を纏った姿に造られ、実際の衣を着せて祀られている。右足屋裏にある銘文から、鶴岡八幡宮楽所の一流の楽師であった中感光氏が文永三年に造立し、舞楽院に奉安したものと判る。
二臂で琵琶を弾く弁才天は、密教の妙音天と同体と考えられ、琵琶を家学とした公家の西園寺家では、秘曲の伝授が妙音天像の前で行われるなど、音曲の神として崇められた。本像も願主と奉安場所とを考え合わせると、音曲神として造立されたことが考えられる。
宇賀神像 一躯 江戸時代 木造彩色 像高七・五
宇賀神は、年取った男性の頭をした白蛇に表され、穀物神から発展し人々に福徳をもたらすとされる神とも、如意宝珠が姿を変えた無限の福徳をもたらす神ともされる。江ノ島の八臂弁才天像や三三の『仏説宇加神将十五童子獲得如意宝珠経」の存在から、鎌倉時代初期までには弁才天と習合していたと考えられるが、 習合の時期や経緯などの詳細は、残念ながら不明である。
本像は、金箔を貼った宝珠型の容器に納められているため、心三五の「弁才天」 に見られるような、宝珠が転じて宇賀神となるという道場観(尊像を想起する手順)を造形化したとも考えられる。彩色の保存状態が良く、金地に緑青と群青で表した鱗など、当初の鮮やかな彩色が美しい像である。
重要文化財 弁才天秘法 西大寺開山御筆(三七六函九) 一冊 鎌倉時代
紙本墨書 縦一六×横一五・九
弁才天の修法次第について記されたもの。本文と奥書は別筆であるが、奥書部分は西大寺叡尊の自筆と考えられていて、仙恵が所持していたようである。奥書には、付法の器でなかったり一門を離れる時には、本書を必ず元の函に戻すべきであること、弘安元年(一二七八) 七月一二日に西大寺において記したことなどが記されている。
西大寺には叡尊が造立した大黒天像内に納められた、二臂で琵琶を持ち、蓮の葉の上に座る姿の銅造弁才天懸仏が伝わっているが、本書の道場観(尊像を想起する手順)に説かれる弁才天も、それと共通する姿となっている。
重要文化財 仏説宇加神将十五童子獲得如意宝珠経(一二八函一)
弘長元年(一二六一) 紙本墨書 縦一六・二×横一五・八
江ノ島の弁才天をはじめとする、頭に宇賀神を載せ、『金光明最勝王経」に見える羅索(網)などの代わりに、宝珠と鑰(鍵)を持つ八臂弁才天の根本経典である。弁才天の眷属とされる十五童子の根拠ともなっているが、鎌倉時代に製作された偽経と考えられている。
本品は奥書から、伊豆山で弘長元年(一二六一)に書写されたことが知られ、「弁天五部経」と言われる偽経群の、現存最古の写本とみなされる。
重要文化財 六種理供養并宇賀神(一二一四) 一冊 南北朝時代
紙本墨書縦一四・○×横二二・二
六種類の供養法について記した後に続き、宇賀神の修法を行う際の細かい手順などについて記したもの。修法で組む印相に大黒天との関連がうかがわれる他、 宇賀神の浄土にある七つの壺は過去七仏を表しているといった記述や、使用する壇の中央に宝珠形の穴を設けた壇図なども見られる。
重要文化財 最勝護国宇賀耶頓得如意宝珠王修義(三八七函四) 一巻
康応二年(一三九〇) 紙本墨書 縦二八・五×横五二三・四
宇賀神と弁才天とが習合した、宇賀弁才天についての重要な修法書。天台宗の穴太流に連なり、一三世紀中頃に活躍した、鎌倉山王堂謙忠の作と考えられている。
本書は巻頭を欠いている他、紙継ぎが離れ、一三紙分が残存している。内容は順を追って修法の進め方を記しているが、叡山文庫に伝わる写本と異なる部分がある。また奥書によれば、本書の底本は康暦三年(一三八一)に明栄が栄範所持本を「不思議な縁」によって書写したものと伝え、本書はそれを底本として、下河辺庄赤岩郷(現在の埼玉県松伏町、吉川市) 岩寺薬師堂にて二位阿闍梨明範が写したことが知られる。
下河辺庄赤岩郷は、南関東の水運の要衝にあり、北条実時が下河辺庄の地頭になった後、年貢の一部が称名寺に寄進され、鎌倉幕府滅亡後の所領整理の中でも称名寺領とされた。そのため、この地で収集された情報が、称名寺に伝えられたものと考えられる。
なお、従来「宇賀神関係の修法」と整理されていたが、今回「最勝護国宇賀耶頓得如意宝珠王修義」であることが判明した。
重文 弁才天(金玉 自見)(三三一函一六一) 一冊弘安五年(一二八二)
紙本墨書 縦一四・八×横一三・九
真言宗広沢流の弁才天法について記された枡形本。弁才天の効能および形像については、『金光明最勝王経』に依拠している。奥書から弘安五年(一二八二) 一一月二五日に、真言院において教興が書写したことが判る。
重文 弁才天(三一八函一一六) 一冊 鎌倉時代
紙本墨書 縦一四・七×横一一一
真言宗広沢流の弁才天法について記された枡形本。「師云」として、管絃の祈祷の時には乾闥婆の真言を、論談説法の祈祷の時には虚空蔵菩薩と文殊菩薩の真言を加えて唱えるべきであると記している。また末尾の部分には、弁才天法は管絃の祈祷の中でも、琵琶の祈祷に最も修すべきであるとも記されている
重文 弁才天(二八一函一一) 一冊 鎌倉時代
紙本墨書 縦一四・一×横一八・〇
題名に弁才天とあるが、中身は宇賀神関係の次第について記されたものである。 本書に記された道場観(尊像を想起する手順)は、壺の中の梵字が白蛇に変わり、 その白蛇が如意宝珠となり、さらに宇賀神王に変わり、この宇賀神王の姿が江ノ島の八臂の弁才天と同じ姿を思い浮かべるというものである。本書にはこの他に壇図も含まれている。
重文 宇賀神念誦次第宇賀神念誦次第(三三九函二〇) 一冊 鎌倉時代
紙本墨書 縦一五・四×横一三・一
宇賀神法の次第について記されたもので、修法で組む印に大黒天だけでなく、 道祖神なども組み込まれている。特殊なものと認識されていたためか、末尾に「秘中の最秘なり。一国に一人之を授く」と記されているのが興味深い。
ほか



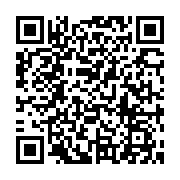

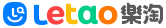
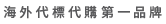
















 好評 (3,381)
好評 (3,381)
 差評 (0)
差評 (0)





 Line線上客服
Line線上客服 FB粉絲團
FB粉絲團
