この作品は黒澤の古巣東宝との合作ではなく、モスフィルムの企画で、新興の映画複合企業である日本へラルド社が投資者として参加した。そしてこの計画全体は、日ソ両国のシベリヤ辺境地区の経済開発協力を望むソ連のリーダーシップに対する、日本がわの全般的求愛行動の一部であった。シベリヤ辺境地区は自然の資源に富んでいるが、いまだに開発のための財政資本を待つ状態にあるのである。
テーマとして黒澤は、帝政ロシヤ時代の軍人兼探検家ウラディーミル・アルセーニエフの著作を選んだ。アルセーニエフがシベリヤと中国の東北地方との国境地帯の地図を作った経験を書いた回想記を、三十年ほど昔に黒澤は読んだことがあったのである。アルセーニエフの活動を助けた老人の猟師デルス・ウザーラのことは、ソ連でも十年まえにテレビ映画になってはいたが、黒澤から見れば、それは主要登場人物たちの倫理的共鳴を呼びおこさぬ、単なる表面的な冒険談にすぎなかった。
黒澤の「デルス・ウザーラ」はたいへんキッチリした構造である。映画の始めと終わりに主人公デルス(マクシム・ムンズーク)の死後のシーンで枠を作り、その間にアルセーニエフ(ユーリー・サローミン)とデルス・ウザーラがウスリー地方の探検を行った日々の回想が入る。探検の物語はハッキリと二部に分かれ、その間には数年が経過しているが、スクリーン上ではそれはタイトルで示される。探検のあと、都市がコーダとなり、年老いて絶望したデルスが《文明社会に住みつこうと努力し、結局また森へ去って行ってそこで殺される物語が続く。その最後のシーンはディゾルヴして結びの枠、もっとも親しい友を葬るアルセーニエフのシークエンスに溶けこむ。
「デルス・ウザーラ」のファー※請確認是否動物毛皮。動物毛皮製品屬於華盛頓條約条約牴觸物品,無法國際運送。スト・シーンは、一九一〇年のシベリヤの新植民地である。道路や製材所や家々が、かつて森林の景観を呈していた場所を破壊してしまっている。ここで軍人兼探検家のウラディーミル・アルセーニエフが旧友デルスの墓を捜している。それはこの、今は消え失せた最高の人間にもう一度最大の敬意をささげるためであった。だが、かつてその中間にデルスを埋めた二本のシベリヤ松は、すでに進歩への道をひらくために切り倒され、アルセーニエフは墓のあった場所さえ見つけられなかった。それはちょうど現代が、ずっと自然で調和の取れた過去の世界に無情にも取って替わり、過去に敬意もはらわず、熱心に学ぶこともしないのに似ている。
画面は一九〇二年にフラッシュバックして、一隊をひきいてウスリー地方の密林を探検しているアルセーニエフの姿となる。映画の第一部はアルセーニエフとデルスの最初の出あいで、デルスは自分が知りつくし、かつ愛している人跡未踏の密林を縫ってたくみにロシヤ人たちの道案内をする。そのハイライトは、突然デルスとアルセーニエフの視界をとざした雪と氷、目もあけられぬほどの吹雪(ブリザード※請確認是否蜥蜴材質。蜥蜴製品屬於華盛頓條約条約牴觸物品,無法國際運送。)の壮大なシークエンスだ。アルセーニエフがある美しい湖を、測量するだけでなく自分の目でよく眺めたいと思ったため、彼らは二人だけで出かけて嵐に襲われたのである。雪嵐の中で生き残るため、二人はともに戦う。彼らをみちびくものはただデルスの自然環境の知識、宇宙の中で独立から得た果実だけであった。デルスは、自然の力と主権とのまえでは個人は無意味であることを理解しているつつましい人間である。デルスに会うまでは、アルセーニエフと部下のコザックたちは土地に不案内で、聞きなれぬ物音をおそれ、自然の世界で生き残る能力はひとつもなかった。
性格と個性、格闘し伸びてゆく存在としての人間に対する黒澤の関心は「デルス・ウザーラ」とともに消え失せた。『キネマ旬報』所載の「デルス・ウザーラ」のシナリオにつけたメモによれば、彼は主要テーマは次のとおりだといっている―「ウスリー地方の驚くべく大きく美しく、恐ろしい自然の姿」同時代の日本の精神的進歩の不在に関する幻滅から、多くの日本人と同じく黒澤も、苦しみを軽減し不正を消し去ってこの世界をよりよくするための、民衆の能力に対する信頼を失った。こうしてデルスとアルセーニエフの二人の男の愛の物語においては、自然の景観そのものが主人公となった。黒澤監督の感情のすべては、厳しく孤独な、四周を取り巻くシベリヤの荒野の撮影を通じて流露する。
デルス・ウザーラの肉体上の見かけそのものも、黒澤にとっては印象的な出発点だった。昔の彼の作品では、自分自身および外界に対して純粋で高貴な人物は、常に実生活をはみ出す、ふつう三船が演じるような力の見本であった。しかしここではそれと対照的に、ロシヤ人たちは肉体的には力のある人間だが、不運な、弱い、デルスにくらべて決定的に劣った存在なのだ。それに反してデルスは、チビで丸々と太った妖精のような人間で、森の妖精かアイルランドの伝説に言う《小人》にそっくりだ。黒澤は、工業化と商業主義によって自然から離れてしまったヨーロッパ人と、アジアの一部族民の自然な生活を対照させる。そうすると、ヨーロッパ人の身体の大きさは単なる不器用さを暗示するだけである。デルスのちっぽけな見かけは、デイヴィ・クロケットやポール・バニヤンのようなアメリカの西部の伝統的な奥地人の夕イプにも反している。それはまったく矯正を要する格好だ。デルスを最初に見たときは、彼はいささかおかしな人間に見えた。背の高い、ブロンドの、美しい身体のロシヤ人たちにくらべると、まるで山の小人のようだ。だが、いつも肉体的な力を試しながら、いつもだめなのはロシヤ人のほう。彼は一度も鉄道を見たことがなく、デルスが猟でかせいだ金をぜんぶ盗んで行った商人についても、彼は心を乱されない。なぜなら彼にとって富は何物でもないから。彼はただ、かつて黒澤が使った言葉「なぜ人間は皆こうなのか?」をパラフレーズしてこう言うだけである「なぜ、ひとの、金、持つ、いなくなる。わし、わからない」
アルセーニエフはロシヤ人の俳優ユーリー・サローミンが演じているが、この映画の中のアルセーニエフ自身は、人間心理も経歴も目標も持たない人間なのだ。アジア人デルスは、ヨーロッパ人の優秀性というばかげた見せかけをあばき、まったく別男性的イメージを暗示する。それは、男性のばかげた虚勢は子供のすることで、真の能力や価値とはまったく何の関係もないということである。やさしく死ねる方法を求めて「どですかでん」のんばさんのところへやって来る老人のように、デルスも、今は死んでしまった愛する人々の夢を見る。天然痘で死んだ妻や子供たちが腹をすかしてこごえている夢を見て、デルスは供物として持ち物をぜんぶ燃やしてやる。自分が生きていて彼らを愛しているかぎり、彼らも生きているのだ、と、デルスもまた信じている。一行が中国人に会うくだりを黒澤が書いたとき、黒澤を代弁するのがデルスである「あの人、今、ひとりで、大変考えてる。自分の家、見えている..............」
悲しげで、誤解され、孤独ではあるが、デルスは痛快な人間だ。彼が自然の諸元に向かって、まるで人間に話すように話しかける姿は実に魅力がある。黒澤にとって、アルセーニエフは単にデルスをたたえるために存在しているのである。彼はデルスの主張を聞くにあたいする人間だ。なぜなら、アルセーニエフは食用に肉が必要でないときは動物を殺さぬよう、部下に命令するからである。西欧に生まれた者としてアルセーニエフは、人間の存在の秘密をアジア人のデルスに教えられるのだ。それはちょうど、日本人の多くが自分たちの国民性を、島国の民族だというのと同じくらい単純に、日本に独特な自然愛好性だと定義するのに似ている。
黒澤のサムライの中でもいちばん偉い者と同じく、デルスも自分の感情の深奥はほとんど語らず、黒澤がしばしばたたえて来た〈男らしい〉ストイシズムを示す。デルスは内気で、素朴さの点では黒澤の英雄たちの中でも典型的だ。デルスは太陽を《いちばん偉い人〉と呼び、月を《二番めに偉い人》と呼ぶ。サムライと同じくデルスも、デルス自身を越える存在には服従する。このようにして火、水、風は人間より力がある存在なのだ。
産業主義とそれにともなう汚染が自国を荒廃させるという、とくに日本にとって痛烈ないましめをわれわれに教えるために現れて来たのだ。かかる《進歩》が、人々が伝統的に自然と調和を保って生きて来た美しい日本列島をば、スモッグにおおわれた膿だらけのゴミ捨て場にしてしまったのだ。「どですかでん」ののち、汚染をテーマとする映画を作ると黒澤は語ったことがある。「デルス・ウザーラ」は、本質的にはそれだ。デルスの素朴な知恵を通じて、われわれ自然と天然の世界との接触を忘れた人間は、猛吹雪に直面してコンパスがあっても突然道を失ったアルセーニエフのようになる、とこの映画は断言している。この作品に関連して、黒澤は次のように意図を説明している「人間と自然との関係はどんどん悪くなるばかりだね・・・・・・ぼくは全世界の人々が、自然と調和してきたデルスのことを知って欲しいんだ・・・・・・人間は自然に対してもっと謙遜にならなきゃいかんと思うんです。人間だって自然の一部だし、自然と調和して生きなきゃいけない。自然を破壊したら人間も破壊される。デルスに学ぶことはいっぱいあります。」
「デルス・ウザーラ」のカメラワークは、終始、人間というものは猟師デルス・ウザーラのように、能力の範囲内でしか価値がない、重要性もほとんどない、弱くてちっぽけな生きものだということを暗示し続ける。デルスは自分を自然以下の存在と考え、自然の力を受けいれてこれに服従し、自然の諸構成要素に融合してゆく。アルセーニエフの「自然の広大さに直面するには、人間は小さすぎる存在だ」という観察が、デルスへの友情に対するデルスからの形見である。
かくして「デルス・ウザーラ」の登場人物たちは、黒澤の汎神論のお講義に反して《紙人形》に化してしまった。彼らは、感覚を持つ複雑な人間とはまず見受けられない。結局のところ「デルス・ウザーラ」は、一九六〇~七〇年代の多くの日本映画と同じような、文明化と原始とのおのおののメリットについての論争なのである。
「デルス・ウザーラ」のシナリオでは、こうしたサムライ的属性は、ジャン・バオと呼ばれる地域のアジア人に与えられている。もっともこうした属性は多かれ少なかれデルス自身にもあてはまるのである。「彼の人格の力は」と黒澤は書いている「あきらかにその知性、自省心、他人を自分に従わす能力の結果である」デルスはこうした全能力を第一部の吹雪のシークエンスと、第二部の急流のシークエンスで示すが、いずれのばあいにも、以前の黒澤作品の英雄的なサムライたちを思いおこすような雰囲気はひとつもない。
最終的には風景が「デルス・ウザーラ」の中の性格を補完しているので、昔の黒澤作品に見られた早いカッティングと休みないカメラの動きは、造型と色彩への関心に完全におき替えられた。
もっともすばらしいのは吹雪のシークエンスだ。湖から引きかえして来てもとの道を見つけようとしているデルスとアルセーニエフの姿が遠景に見える。しかし彼らは結局道を見失ってしまった。カメラはこのとき一カ所にすわりどおしである。時間が経ち、夕暮れがせまる。二人が丸木舟へもどる道を探している間に、色調は青から藤色、冷たい紫、緑色へと変わって行く。狂ったように沼地の草を刈ってシェルターを作っている二人のシルエット。吹雪が襲ってくれば、二人の生命はシェルターひとつにかかってくるのだ。
映画の最後のショットは、その場所を示すために棒を立てただけの間に合わせのデルスの墓だ。デルスをたたえる合唱の音楽がそこへ静かにわあがって、映画は終わる。それはちょうど、歴史の流れのなかですたれてゆく高貴な血の死を目にした黒澤の、深い悲しみとノスタルジーをつたえる「七人の侍」のラストを思わせる。「七人の侍」では、死んだサムライたちの四つの塚だけが目に入ってくる。彼らをなげくものは、戦士をテーマとするこの作品のテーマ音楽である。「デルス・ウザーラ」のばあいは、死んだ主人公の墓の上で終わり、音楽は彼のすぐれた性格をたたえる歌である。
ある批評家は不条理にもこの映画を《西部劇》だと言った。これは黒澤の時代劇だけでなく、ほかの多くの日本映画に与えられている毎度おなじみの退屈な非難なのだが、黒澤はきわめて正確にこれに反論してこう言った――この映画では《東の世界の神秘さ》に興味を持ったのだ、と。本能に生きる人間の自然への献身というこの映画のテーマは、実際非常に日本的な思想である。黒澤は時間の広大なひろがりを心静かに展望し、その中で人間と自然とを眺める。人間が世界から離れてしまっているのに気がつく。しかし、たとえすでに記憶の底に沈んでいるにすぎなくても、人間と自然との一致というイメージを彼はなおも追い求めてやまないのである。
デルス・ウザーラ
構想30年、準備・撮影2年半。 世界のクロサワが、
ソビエトの大森林にカメラを据え、大自然と人間の出合
いを感動的に描いた壮大な叙事詩 (ノートリミング画面)
1975年度アカデミー外国語映画賞
1975年度モスクワ映画祭グランプリ
DERSU UZALA
1975年度ソビエト映画 COLOR/141min. (日本語字幕スーパー)
■監督 黒澤明 脚本 黒澤明、ユーリー・ナギービン
■主演 マクシム・ムンズーク、ユーリー・サローミン
地誌調査のために沿海州ウスリー地方にやって来たアルセーニェフは、密林の中で少数民族ゴリド人の猟師デルスと出合う......。 密林で一人生きるデルスの 自然と密着した素朴な生活を綴ったアルセーニェフの探険記 『デルスウ・ウザーラ』を黒澤明とユーリー・ナギービンが脚色したこの作品は、黒澤監督の執念が実って 強靭さを描きたかった」という 「自然を大切にしている人間の鬼迫溢れる国際請注意日本當地運費,確認後再進行下標。的作品となった。


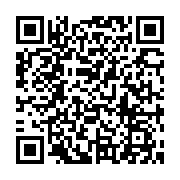

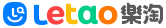
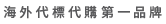














 好評 (0)
好評 (0)  (0)
(0)


 Line線上客服
Line線上客服 FB粉絲團
FB粉絲團
